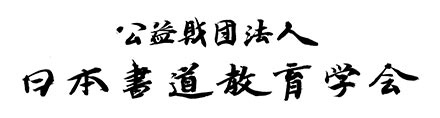書道専攻科講座
原則として書道基礎科を修了された方を対象とした講座です。
基礎科と同様「楷書編」「行書編」「草書編」「かな編」に分かれており、それに「篆隷編」が加わって、より深い学習を行えるようになっています。
楷書編

自分の好きなものばかりに偏ることなく、奥行きの深い書道のなかで書技を拡大できるようにします。まず多くの書風を理解し、書技の向上に役立て、自分の持っている長所を広い範囲から引き出す。専攻科講座の楷書編はこういう考え方に従って編集されています。
また、「学習指導書」には、時には教科書よりも詳しい講義が載っています。
行書編
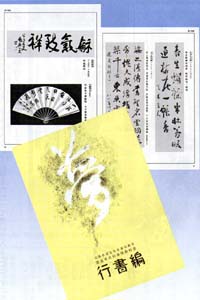
教科書
気脈はすべての書体に必要なことであり、古人は「断処皆連なる」と言っています。すなわち切れた部分がみな連なっているというのは、そこに気脈があるからで、行書はその気脈を一番会得しやすい書体です。実画と実画の間の空間は、最短距離の通路ではなく、そこでは大きく筆が旋回したり躍動しているものです。このような空間の筆意を生むわけですから、気脈の研究は、かかって空画の研究にあるといえます。専攻科の行書編では、こういうことを中心に学習します。
学習指導書
通信教育で学びながら、ときには上達のコツを見いだせなかったり、要領が分からないときがあるかも知れません。そういうとき、みなさんを絶えず励まし、正しい方向へ導いていくのが、学習指導書です。
草書編
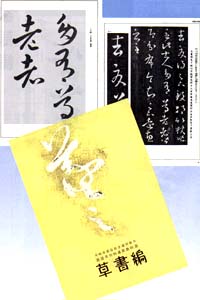
教科書
草書といえば、やわらかく、スラスラと書くのが良いと思われますが、誤りです。草書にも、楷書のような強さが加わらなければ、引き締まった線や形になりません。書はすべて変化と統一が巧みに織り成されたときに、その美しさを発揮します。特に草書では、字形に変化が多いので、このことを忘れてはなりません。さらに、草書には類似の字形が多くあります。だから古人の残した形に従い。誤読されないよう文字を正しく学ばなければなりません。専攻科の教科書では、特にこれらのことに注意しながら学習するようになります。
学習指導書
草書は「草書体」として特別に学ばなければ習得できない書体ですが、わかりやすい解説を加えながら学習の方向を示唆します。
かな編

教科書
かなの実技を向上させるには、少ない分量を、くわしく習いおぼえることが大切です。どんな平行線でも曲線でも、円でも点でも、自由に書けるように鍛錬することが大切です。手本をよく見きわめて、よくまねることです。紙も、手紙を縦長にしたり、横長にしたりしてみれば、字の配置、空間の取り方、行数、字数の使い分けもうまくなります。また教科書の書式に従って、条幅、額などの紙も使って練習し、腕を磨いて下さい。そして最後は、自分でかな作品の創作をします。
学習指導書
教科書にあるかなの理論については、よく読んで頭に入れておいて下さい。そして習った部分を、手本をみないで記憶をたどって書いてみることです。指導書がこうした学習上の注意を促します。
篆隷編
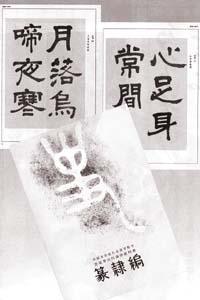
教科書
篆書・隷書は、展覧会などの作品や篆刻に用いられており、実用的には看板とか標柱、石碑、表札などに使用されますが、あまり一般的なものではありません。しかし、漢字を研究し、書道を学ぶ者には、ないがしろにできないものです。篆書・隷書は、楷書と違った筆順、字形ですから、古法帖を学ぶときも、筆使い、筆さばき、筆順や字形などを、よくみきわめて練習するように心がけてください。このような学習目標と内容を盛り込んで、篆隷編の教科書は編修されております。
学習指導書
こうした教科書の内容をかみくだき、わかりやすく説明したのが学習指導書です。学校にたとえていえば、ちょうど先生のようなつとめを果たしているのが学習指導書といえます。
受講期間
受講期間は24ヶ月になります。課題の提出は楷書・行書・草書・かな・篆隷 各編5回と総括課題の計6回+最終終了試験課題の合計31回あります。
受講料
本会通信教育の受講生および修了生が他の講座を申し込む場合、入学金2,500円が免除されます。不二誌会員、書学院受講生も同額免除されます。
受講料
| 本人受講 | |
|---|---|
| 入学金 | 2,500円 |
| 受講料 | 40,200円 |
| 合計 | 42,700円 |
※受講費はいずれも税込です。
※書道専攻科講座には、家族受講の制度はありません。
※別途、送料がかかります。
団体受講
10名以上の団体で受講される場合、その奨励の意味を含めて、各人の入学金の一部(1,500円)が免除されます。講座および全納・分納に関わりなく、全体で10名以上であればこの特典は適用されます。
追加受講も可能です。ただし、家族受講はその数に加えることは出来ますが、入学金の一部免除の特典は受けられません。